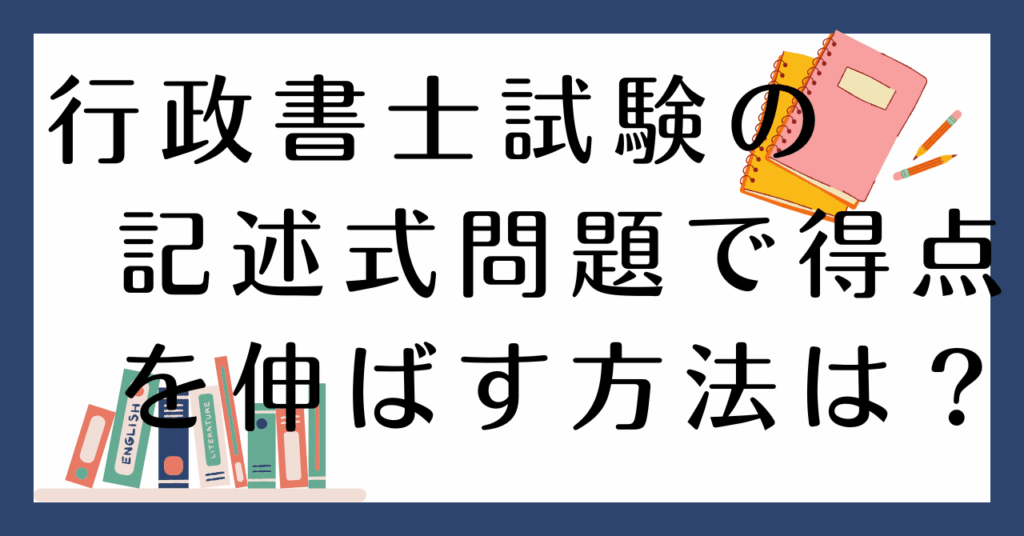
行政書士試験問の中で、配点の大きなウエイトを占めているのが「記述式問題」です。
この記述式問題で、得点をいかに伸ばせるかが行政書士試験の合格へのポイントになります。
記述式問題は配点が高い
まずは、行政書士試験において、各問題がどのくらいの配点であるかを確認します。
| 科目 | 問題種類 | 出題数 | 1問配点 | 合計配点 |
|---|---|---|---|---|
| 法令等科目 | 択一式 | 40問 | 4点 | 160点 |
| 多肢選択式 | 12問 | 2点 | 24点 | |
| 記述式 | 3問 | 20点 | 60点 | |
| 基礎知識 | 14問 | 4点 | 56点 |
択一式問題は合計配点160点と一番大きい配点ウェイトを占めているのですが、出題数も40問と多いので、得点を伸ばすためには1問でも多くの問題に正解する必要があります。
次に配点ウェイトが大きいのは記述式問題で、合計配点は60点です。出題数は3問だけなので、1問でもきちっと正解できれば得点を20点伸ばすことができます。
ただし、そう簡単にいかないのが「記述式問題の難しさ」です。
記述式問題の出題形式
記述式問題は、他の択一式問題や多肢選択式問題と異なり、マークシートの正解肢を塗りつぶして解答するのではなく、40字程度の文章を書いて解答する形式になります。
問題に対して、自分の言葉で文章を書いて解答する必要があるため、受験生の多くが苦手意識を持っているのではないでしょうか。
記述式問題は、文章に書いて解答するため、択一式問題とは違った練習が必要となりますが、条文や判例の内容を記述させるものがほとんどです。つまり、記述式問題についても条文や判例知識が重要になります。これは択一式問題と共通です。
なので、記述式問題のために何か新しい知識が必要になるというよりは、択一式問題を解答するための知識をしっかり押さえることが重要となります。
記述式問題では部分点がもらえる
記述式問題で意識したいのが、「完全正解ではなくても、キーワードが書けていれば部分点がもらえる」ということです。
正解文と全く同じ内容で解答できなくても、いくつかのポイントとなるキーワードが書けていれで、それぞれ6点、8点、12点といった部分点がもらえます。
なので、どうしても完全正解できそうもないときは、ひとつでも多くのキーワードを書くことで、部分点をとっていくことが重要です。
記述式問題を解答するための4つの手順
記述式問題を解くためには、4つの手順があります。
- ①問題となっている状況を把握する
-
登場人物が誰なのか、どのような点が争点として問題になっているのか、といった点を確認します。試験問題の余白に、人物相関図や争点を書き込んで図式化するもの効果的です。
- ②解答すべきポイントを把握する
-
記述式の問題の多くは、条文や過去の判例に当てはめて考えさせる問題が出題されます。
例えば、
「~において取消訴訟を提起する場合、裁判所は、どのような理由により、どのような判決をするか、40字程度で答えなさい」
となったり、
「誰が誰に対して、どのような要件の下で、どのような請求をすることができるか、40字程度で答えなさい」
といった問題文で出題されます。
それぞれの問題文において、「どのような理由」「どのような判決」「誰が」「誰に」「どのような要件」「どのような請求」といった答えるべき解答ポイントをきちっと把握することが重要です。
- ③問題文の答えるべきポイントに沿って文章を作る
-
「~において取消訴訟を提起する場合、裁判所は、どのような理由により、どのような判決をするか、40字程度で答えなさい」という問題があった場合の、答えるべきポイントは、
「どのような理由により」
「どのような判決するか」
です。
また、「誰が誰に対して、どのような要件の下で、どのような請求をすることができるか、40字程度で答えなさい」という問題があった場合の、答えるべきポイントは、
「誰が」
「誰に」
「どのような要件の下で」
「どのような請求をすることができる」
です。
よって、問題文に対応する解答文の構成としては、
「どのような理由により」 ← 原告適格を欠くという理由
「どのような判決するか」 ← 却下判決をする
となった場合は、解答文は「原告適格を欠くという理由によって却下判決をすることとなる」と書きます。
もう一つの問題例においては、
「誰が」 ← Aは
「誰に」 ← Bに
「どのような要件の下で」 ← Cの追認を得られたときを除く
「どのような請求をすることができる」 ← 損害賠償請求をすることができる
となった場合は、解答文は「AはBに対して、Cの追認を得られたときを除いて、損害賠償請求をすることができる」と書きます。
つまりは、問題文の問いの内容に沿った形で解答文を作っていくことが重要です。
- ④記述式問題3問すべてを完全解答することを目指さない
-
記述式問題の配点は、行政法で1問20点、民法で2問40点、合計60点です。3問とも解答文がスラスラと書けるようなら60点を目指してもいいと思います。
ただし、受験生の多くは解答文を作るのに苦労します。「答えるべき判例や条文が思い出せない」「何を書いたらいいのかわからない」、といった状況に陥ってしまいます。
そんな時こそ、解答すべきキーワードを書いて、部分点を積み上げて、1点でも高得点を目指しましょう。
つまりは、記述式問題では、最初から満点60点を目指さずに、解答すべきキーワードを1つでも書いて部分点を積み上げて、40点前後の得点を目指すことが現実的な戦略です。
2色の蛍光マーカーが役に立つ
行政書士の試験会場は、蛍光マーカーの持ち込みが可能です。
私自身、試験では2色の蛍光マーカーを持ち込んで、問題文の状況を把握するために緑色の線、解答すべきポイントにはピンク色の線を引いて、理解しやすくする工夫をしていました。
例えば以下のように2色のマーカーを引くと、問題文が理解しやすくなります。
「AがBに対して有する貸金債権の担保として、Bが所有する乙建物につき抵当権が設定され、設定登記が経由された。当該貸金債権につきBが債務不履行に陥った後、乙建物が火災によって焼失し、Bの保険会社Cに対する火災保険金債権が発生した。Aがこの保険金に対して優先弁済権を行使するためには、民法の規定および判例に照らし、どのような法的手段によって何をしなければならないか。40 字程度で記述しなさい。」
この2色の蛍光マーカー作戦は、出題された問題文で、「何が問題になっているのか」、「何を答えればいいのか」が頭の中で整理することができるので、とてもおススメです。

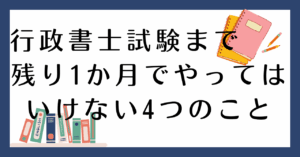
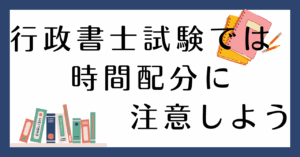
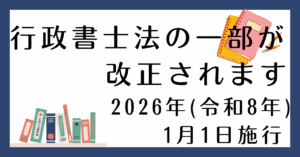
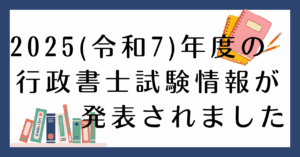
コメント