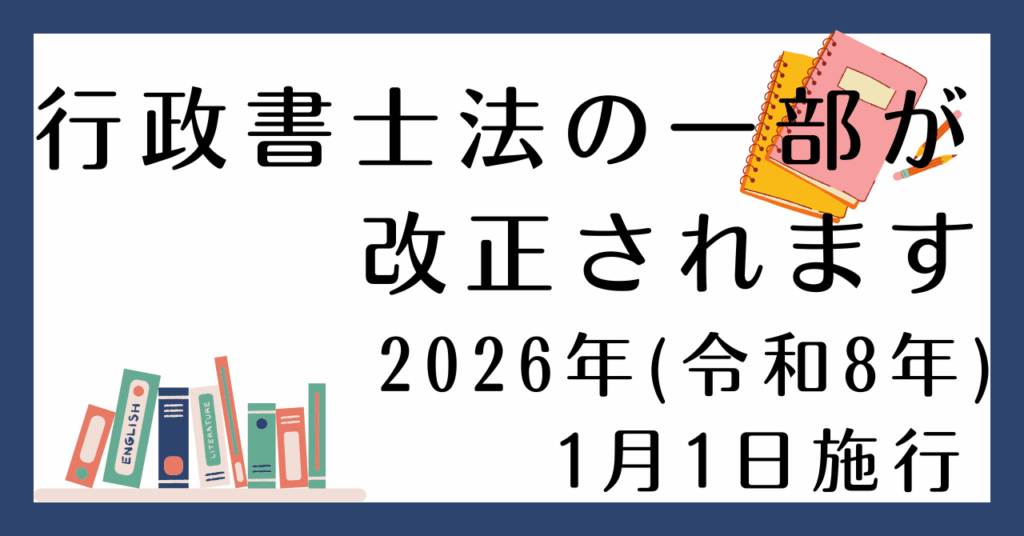
今回の行政書士法の改正は、全部で5点あります。
- 「行政書士の使命」について
- 「職責」について
- 「特定行政書士の業務範囲の拡大」について
- 「業務の制限規定の趣旨の明確化」について
- 「両罰規定の整備」について
「行政書士の使命」について
行政書士法第1条の目的を使命に改め、
「行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとすること。」
とされました。
| 新条文 | 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とする。 |
| 旧条文 | この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。 |
「職責」について
行政書士法第1条の2に職責として、
「①行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。②行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。」
とされました。
| 新条文 | 第一条の二 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 2 行政書士は、その業務を行うに当たつては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。 |
| 旧条文 | (条文新設のため旧条文なし) |
「特定行政書士の業務範囲の拡大」について
行政書士法第1条の4第1項第2号の特定行政書士が行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大することとされました。
| 新条文 | 第一条の四 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 一 〈略〉 二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。 |
| 旧条文 | 第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 一 〈略〉 二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。 |
「業務の制限規定の趣旨の明確化」について
行政書士法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、
「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
の文言を加え、その趣旨が明確にされました。
法第1条の3の「報酬を得て」とは、書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることですが、この改正によって、「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。
| 新条文 | (業務の制限)第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。 |
| 旧条文 | (業務の制限)第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。 |
「両罰規定の整備」について
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。
| 新条文 | 第二十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十一条の二(業務の制限)、第二十二条の四(名称の使用制限)、第二十三条第二項(帳簿の備付及び保存)又は前条(調査記録簿等の記載・記録・保存、立ち入り検査など)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
| 旧条文 | 第二十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一号(調査記録簿等の記載・記録・保存など)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。 |
今回の法改正は、いつの試験から出題される?
今回の行政書士法改正は、2026年(令和8年)1月1日から施行されます。そこで、今回の行政書士法改正が、いつの行政書士試験から対象となるのか気になるところです。
行政書士試験センターから公表された2025(令和7)年度の試験概要によれば、
| 試験科目 | 試験内容 |
|---|---|
| 行政書士の業務に関し必要な法令等(出題数46題) | 憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、令和7年4月1日現在施行されている法令に関して出題される |
| 行政書士の業務に関し必要な基礎知識(出題数14題) | 一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、情報通信・個人情報保護及び文章理解の中からそれぞれ出題し、法令については、令和7年4月1日現在施行されている法令に関して出題される |
となっていますので、行政書士試験に対象となるのは、2026年度(令和8年度)の試験からとなります。
2026年度の試験を受験する際は、今回の行政法改正についてはきちんと押さえておいたほうがよさそうですね。

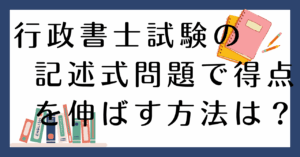
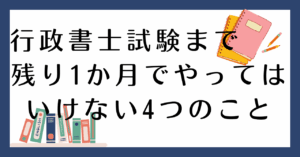
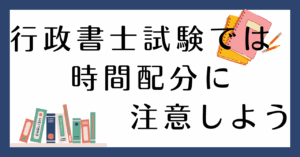
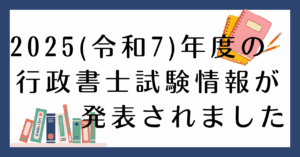
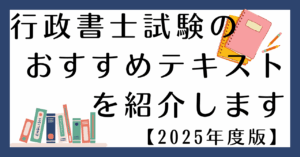
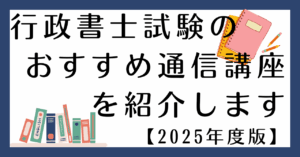
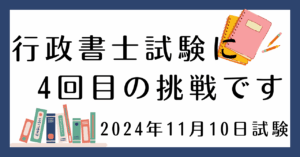
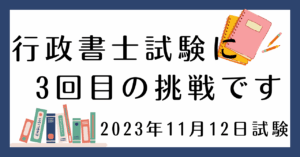
コメント