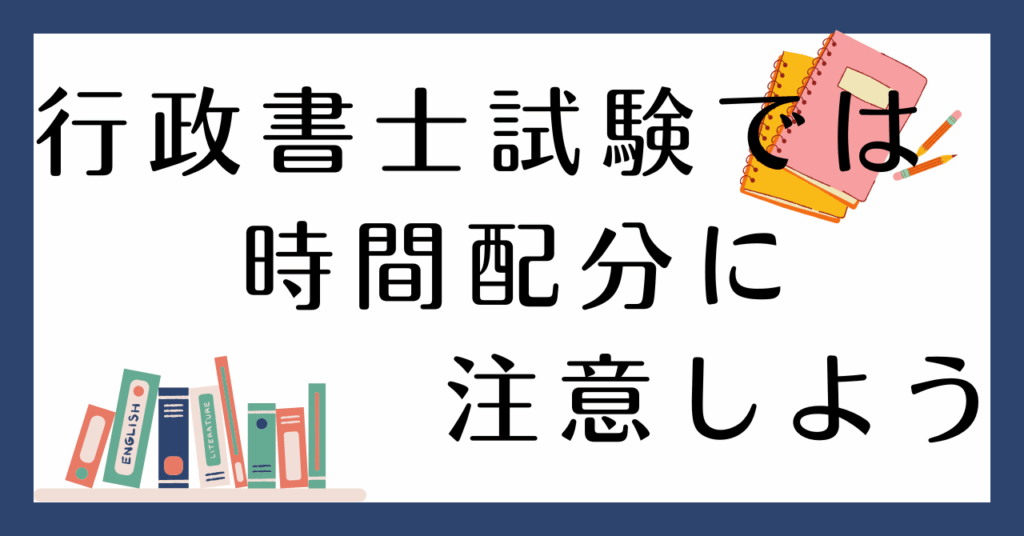
行政書士試験を受験する際にとても大事なことは、
「試験時間内にすべての問題に目を通し、自分が解ける問題を解答すること」
です。
試験では、初めて接する論点だったり、まったく勉強していない分野だったり、自分にとっては難問に該当するものが必ず出題されます。
このような難問が解けないことは問題ではありません。そんな問題は、受験者全員解けない問題と思って割り切ることです。
大事なのは、すべての問題に目を通し、自分が解ける問題と解けない難問を判断することです。
そこで大事になってくるのが、試験の時間配分です。
つまりは、どの問題にどのくらいの時間をかけるかです。
問題を解く順番と時間配分を考えてみよう
問題を解く時間配分と同じく、どの順番で解くかも重要です。
個人的におすすめするのは、試験の最初の頃に、重要科目である「民法」と「行政法」に着手することです。
例年の出題数は19問、問題を解くための時間配分は30分、1問あたり約1分30秒で解くことになります。
例年の出題数は9問、問題を解くための時間配分は30分、1問あたり約3分30秒で解くことになります。ここまでで経過時間は60分、試験時間の1/3です。
例年の出題数は12問(憲法4問・行政法8問)、問題を解くための時間配分は15分、1問あたり約1分で解くことになります。ここまでで経過時間は75分です。
例年の出題数は3問(民法2問・行政法1問)、問題を解くための時間配分は25分、1問あたり約9分で解くことになります。ここまでで経過時間は100分です。
例年の出題数は2問、問題を解くための時間配分は5分、1問あたり約2分30秒で解くことになります。ここまでで経過時間は105分です。
例年の出題数は5問、問題を解くための時間配分は15分、1問あたり約3分で解くことになります。ここまでで経過時間は120分、試験時間の2/3です。
例年の出題数は5問、問題を解くための時間配分は15分、1問あたり約3分で解くことになります。ここまでで経過時間は135分です。
例年の出題数は14問、問題を解くための時間配分は40分、1問あたり約3分で解くことになります。ここまでで経過時間は175分、残り時間5分です。
試験時間も残り5分です。今一度解答用紙に誤記入がないかを確認しましょう。
解答欄がズレてマークしていないか、分からない問題を飛ばしたのにその問題番号欄に次の問題の解答をマークしていないか、などを確認します。
以上を表にまとめること、このようになります。
| 科目 | 問題種類 | 科目 | 出題数 | 時間配分 | 経過時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法令等科目 | 択一式 | 行政法 | 19問 | 30分 | 30分 |
| 民法 | 9問 | 30分 | 60分 | ||
| 多肢選択式 | 12問 | 15分 | 75分 | ||
| 記述式 | 3問 | 25分 | 100分 | ||
| 択一式 | 基礎法学 | 2問 | 5分 | 105分 | |
| 憲法 | 5問 | 15分 | 120分 | ||
| 商法 | 5問 | 15分 | 135分 | ||
| 基礎知識 | 14問 | 40分 | 175分 | ||
必ず模試を受けて、時間配分を意識して問題を解くこと
行政書士試験の本試験で、いきなりこの時間配分を意識して問題を解こうと望んでも、なかなかうまくいかないと思います。
なので、どの模擬試験でも構いませんので、必ず1~2回は受けて、時間配分がうまくいくかどうかをチェックするようにしてください。
事前に時間配分の感覚を体験することがとても重要です!

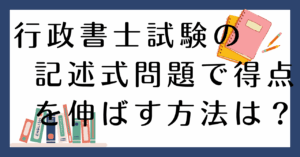
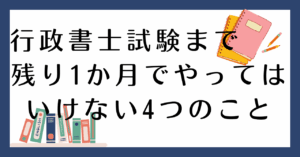
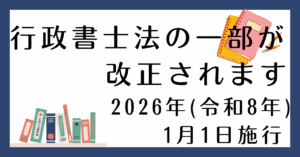
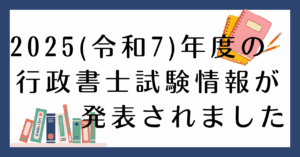
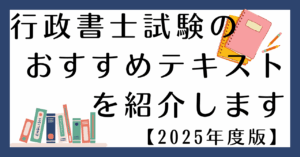
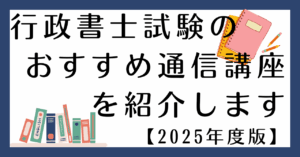
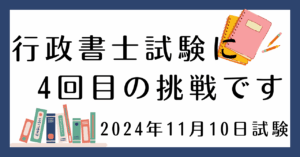
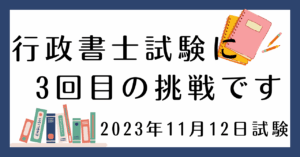
コメント